おいしいたまごを創る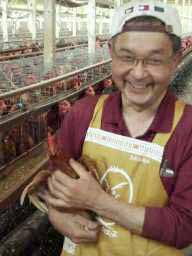
規模拡大競争曲
物価の優等生と言われるようになって久しいたまごですが、いうまでもなくそれは生産量の増加によるものです。
過去、生産量の増加(=規模拡大)は農家養鶏レベルでは次のような過程を経てきたかと思います。
1・利益が上がり、さらにより多くの利益をもとめての規模拡大
2・その結果単位利益が下り一定収入を確保するため更に規模拡大。
3・生産量ますます増大、そして相場は、さらに低迷。そのため 更なる規模拡大(大型企業養鶏では別の企業の論理があろうけれども結果は同じ でありましょう)この段階ですでに生産量は市場規模(需要)をこえてしまっております。そして現在では
4・ 2・3・のころよりは拡大指向は少なくなったが基本的には増大方向にある。
業界をとりまくソフト、ハード両面でのめざましい進歩はこれらの事をごく自然に実践ならしめました。しかしながら、市場規模をこえた生産は相場の下落(=生産原価割れ)を招くことは明らかです。
こうした過程のなかで経営者の最大の理念は販売を”相場”で
規制されたなかでの自己の利益の追及、その手段の一つとして徹底した経費削減といえましょう。しかし、私ども、資本も人材も能力もない小規模農家養鶏はこうした市場原理による相場形成とコスト削減競争のなかに組み入れられてしまってはとても勝ち目はありません。それでは私どもが生き残るためにはどうしたらよいのでしょうか。
それは、こうしたコスト競争と相場形成の循環から抜け出すことによってのみ可能と考えます。
特殊卵は本物か
最近、ヨード強化、ビタミン強化等のいわゆる”特殊卵”がスーパー等のたまご売り場を賑わせて、あるいは個々の養鶏場が全国いたる処で”特殊卵”の直売に力を入れ始めています事もこうしたながれの一環でありましょう。それはそれなりのニーズがあり否定するつもりはありません。
しかし、やはり何か釈然といたしません。
何か不自然なのであります。
どこが不自然なのか?それは次のような事と考えます。
即ち、こうした”特殊卵”の多くは相場の低迷による経営上の観点〜少しでも高く売りたいという〜からの発想であり、消費者のニーズから発生したものではないという事ではないでしょうか
もちろん、経費削減、少しでも有利な販売は経営上の鉄則であり必要なことでしょう。しかし他業界〜畜産に限らず〜をみた時、きびしい競争のなかでいかに自社製品を売り込むか、そのために製品の中にいかに消費者ニーズを取り込みそしていかにアピールするか、そのことに懸命に心血をそそいでいます。
翻って、我が業界を思うとき、そうした考えがあまりにも希薄であることを痛感させられます。相場低迷時はもとより、ゆとりがある高卵価時であっても、否、高卵価時であればあるほど高慢であることが多いのに気が付きます。(勿論、すばらしい経営哲学をお持ちの方も多々おられますが。)
消費者ニーズを取り込むという意味では大手飼料メーカーが全国規模で展開しております例えばヨード卵、ビタ卵E等は需要の掘り起こしという点では寄与していると思います。
むしろ、個々の養鶏場が”特殊卵”として直売している品物を実際に購入してみると、疑問符を投げ掛けたくなるようなものが少なくないようです。
相場から脱却
生産者は生産に専念すべき、との議論もありましょうがそれは市場原理による相場とコスト競争の輪廻のなかだけでの正論ではないでしょうか。
相場環境からの脱却をはかるには、それまでのあらゆる常識を考え直すろとが必要と思います。従来、養鶏家のなかには鶏の専門家であり販売にはほとんど無関心だったという方が少なくないように思われます。
しかし、生産量が市場規模を超えるようになり消費の大幅な拡大が望めない今後、小規模養鶏農家が生き残るためには、消費者との接点を模索し、単に名前だけの”特殊卵”ではなく真に消費者ニーズに応えるたまごを生産しそれを地道にアピールしていくことが必要と考えます。
それは決して過去の考え方にとらわれることなく、農家だけの自己満足に陥ることなく、また消費者に迎合するものでもなく、むしろ消費者を教育する位の心構えを持ってです。
そのことが笹崎氏の提唱する”楽農”に通じまた、”第四次産業化”への道のりの第一歩ではないでしょうか。
安いたまごと安いエサ
”たまごは安いもの”というのが一般通念となり、現実に安いたまごが市場に氾濫している中で、ともすると”高く売りたい”という経営者サイドの願望が優先になりがちですが、消費者に高い評価をしていただくためにはどんなものでなければならないか、生産者は消費者に謙虚に耳を傾け、そこから消費者ニーズをくみとる事がまず第一と考えます。
そんなとき”最近のたまごは以前のに比べてどうも水っぽく味にこくがない、こくのあるおいしいたまごは・・・。”という話をときどき耳にします。これこそが市場に氾濫する安いたまごにたいしてのアンチテーゼであり、消費者のニーズではないのでしょうか。
ウ ィンドレス鶏舎に代表される器材(ハードウェア)の進歩が超高密度飼養(一坪当たり100羽超)を可能にし、その結果(それだけではないが)の相場の低落が経営の効率化ー経費削減ーの要求を高めたことは先に述べました。ご承知の通り飼料費が経費の過半を占める現状では経費削減は経費節減を意味します。そして経営者は複数の飼料メーカーを競合させ、安い飼料の購入に懸命になりました。飼料費単価が安いことがある種のステータスとさえ思われました(規模によるスケールメリット、交渉力、etc、)そんな中で飼料各社は安い飼料の開発に力を注ぎます 各研究機関での研究レベルでの話も良いたまごを多量に生ませるための研究となります。
ただしこれらの研究開発のテーマとなる”よいたまご”とは”殻の厚い(強い)””ハウユニットのよい(卵白が濃い)”というものであり(勿論これらは必要なことですが)先ほど述べた”おいしさ”という本来の消費者ニーズには物足りないものでした。即ち、おいしいたまご、という研究は殆どなされていないのが現状です。ー”おいしさ”ということは数値化しにくく、また個人差があり研究対象にはなりにくい、とのことですが、やはり”おいしいたまご”というテーマはあると思います。
こうして”殻の厚い””ハウユニットのよい””多量にうませる”ことの栄養研究がすすめられました。それは、どんな栄養が最低限どのくらい必要か、あるいは入れなくても産卵に影響ないか、というものであるように思えます。そして、それ以外の栄養素は”無駄”なもの(実はおいしさのもとなのでもあります。)として次々と排除されてきました。
つまり、安い飼料の研究開発というのは目的はそうではなかったのですが、結果的においしさの「素」の排除の研究だったといっても過言ではないと思えます。
飼料メーカーのために付け加えますが、各社ともトップブランドのものは本当の意味でよい餌だと思います。ただそれは大変に高価で現状の相場環境では養鶏場のほうがなかなか使いきれないというのが実態かと思います。
おいしい卵はエサから
こうした価格形成環境のなかで、たまごは物価の優等生と言われながら市場の拡大を続けてきました。
先にも述べましたように、このままでは私ども小規模養鶏はやってゆけなくなりますが、しかしまた、こうした市場のたまごに満足していない消費者が(お客様)いることも事実なのです。
こうした人たちに”昔のようなおいしいたまご”をコストを吸収し得る”適正価格”でご利用いただくことが小規模農家養鶏の今後の生き残るおそらくは唯一の道とわたしは信じます。
昔の鶏は土の上を運動していたからたまごがおいしかった、今のような狭いケージ飼いでは美味いたまごになるわけがない・・・という説もありますが、決してそのようなことはありません。エサによってずいぶんと味が変わってくるものです。
今様の方法(一坪100羽を超える超高密度飼養のウインドレス鶏舎はどうなのか私は存じませんが。)でもえさの工夫によっては”昔のようなおいしいたまご”を甦らせることはかなりの程度可能なのです。
”かなりの程度”と言いましたがこれがクセモノでして、えさの工夫の程度によっておいしさの甦り方も
”適当な程度”にも
”かなりな程度”にも
あるいは”いいかげんな程度”にもなりましょう。
どの”程度”にするかは各経営者の判断するところでありましょう。私自身は、市場に氾濫する安いたまごに対抗するということではやはり、限りなく”かなりの程度"に近付けるべきと考え、また実際にそのようにやっております。
"かなりの程度"に近付ければ近付けるほど当然コストが嵩み、かといって市場価格をまるっきり無視した高値にするわけにもいかず、たえず悩んでいます。しかし、いろいろ波風はありますが、そして僅かづつではありますが”おいしいたまご”として確実に評価をしていただきつつあります。
味のちがいは?

もっとも、おいしさの"程度"の差といっても所詮はたまごはたまごであり、ごく僅かなものです。差がまったくわからないとい人もたくさんおります。いえ、むしろわからない人のほうが遥かに多いようです。
ーー確証はありませんが愛煙家ほど差がわからないようです。逆に女性、ちいさな子供ほど味の差がわかるようですーー
私の農場のたまごも前述のように少しづつではありますが、確実に消費者にご理解をいただけるようになって来ましたが、なぜか養鶏経営者の皆様には殆ど評価していただけません。養鶏経営者は”たまごはたまご、味の差なんてあるわけがない。”と主張される方がほとんどです。わたしの家族ですら同様でしてお客様が”ここのたまごは他のとはぜんぜんちがう。コクがあっておいしい。”といってわざわざ遠方から買いにこられるのを見て、そんなものなのか、と改めて自覚させられているのが実情です。こうした、経営者自身がおいしさの差を感じられない養鶏場のたまごは"昔のようなおいしいたまご”はあまり期待はできないかもしれません。
なぜならたまごの味はすべて同じ、と考えるとどうしても”無駄”(おいしさのもと)は排除した安いエサを使いたくなるからです。
高い自家配
”複合汚染”以後安心、安全へニーズからの自家配合飼料にたいする評価が高まりよいエサ、よいたまごの代名詞のような受け止めかたえをするむきがあり、一部の生協等は自家配合であることが取引の条件であるやに聞きます。しかしこれとても経営者の”程度”の考えかたによりずいぶんと違ったたまごになるでしょう。実際、私のところでは自家配合をしておりますがいわゆる、安いエサを作ろうと思えば驚くほど安く出来、”おいしいたまご”にしようと思えば相当にコストがかかってしまいます。
自家配合も
1・エサを安くするための自家配合
2・たまごのおいしさのための自家配合
の二通りにわかれるかと思います。
また、配合飼料にもすばらしい高品質のものもあります。
要は、自家配合飼料か市販配合飼料か、という事ではなく、消費者ーお客様ーのたまごの”程度”に対してのニーズであり、また生産者自身のおいしいたまごへの認識度と取り組む姿勢ということになりましょう。
市場の開拓
こうした、おいしさの”程度”を評価していただける市場は、価格重視あるいは”たまごはたまご、味の差なんか無い。”という一般市場規模よりはるかに少ないのですが、しかし評価していただけるお客さま層が必ずあることも事実なのです。もっとも極端なほうが一個500円の烏骨鷄のたまごであり、他には、例えば完全な自然放牧鶏(・・といえるのは一羽当り少なくとも10坪以上は必要でしょう。10羽に一坪ではありません!)の一個300円のたまごがあるかもしれません。しかし一個500円、300円というのは通常テーブルエッグとしてはあまりにも一般的ではないでしょう。
前半に述べましたように、こうした市場のとは違うたまごの存在をお客さまにアピールして、安心、安全性はもとより”おいしさ”の違いを知っていただき、それを”適正価格”で評価していただくべく努力することこそ、私ども小規模養鶏農家に今後課せられた課題といえましょう。
楽農へトライ
鉄屋さんが”やわらかあたま”で直接消費者にセマってくる今日の時世、畜産農家が、いかによい成績を出そうとも、いかに有機農法を実践しても、それだけでは一般社会から見れば単なる自己満足としか見られないのではないのでしょうか。
敢えて繰り返しましが、こうした課題に取り組むことが笹崎氏の提唱する”楽農”に通じ、また、”第四次産業化”への道のりの第一歩ではないでしょうか。
業界雑感、思いつくまま述べてみました。
かくいう私、二年前倉庫を店舗として改装、小売直売を始めましたが、まだ経営に寄与するまでに至りません。
それでもお客さまから、
”よそから頂いたのだがおいしかったので買いにきた。”
”一度ここのたまごを食べたらほかのたまごを食べられなくなってしまった。”
”子供がいままで生たまごを食べなかったのだけれど、ここのたまごだと食べるんだ。”
”ここのたまごは美味いんだってね、なにか違うのかい、試しに買いにきた。”
などという声を聞くと大変うれしくなり、 いままでとは違種の仕事のよろこびのようなものを感じます。反面、お客さまとは恐いもの、なにか不具合いがあるとたちまち遠ざかってしまいます不具合いをクレームとして申し出ていただけるお客さまには非常に有り難い存在です。
たまごと豚肉では直売における形態、条件は違います。あるいは糞尿処理の問題などたまごとは違った難しさがありましょうが基本的な問題ではこれまでの内容の養鶏を養豚、酪農に、たまごを豚肉、牛肉に置き換えることが可能ではないでしょうか。洩れ承け賜るところによれば、養豚業界は養鶏ほどの急激な規模拡大はなく、相場とコストの問題もさほど大きくはない、との事ですが農産物輸入自由化の問題とも絡み今後、複雑な様相になるのではないでしょうか。
今後起こるえあろういろいろな問題に、消費者の皆様と畜産業界全体とで協力してゆくことができるようになれば、と願っております。
(本稿は雑誌『心友』1990年9月発行の第41号に掲載したものです。)
|