|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
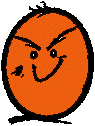 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り
(2000年版)
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り緊急号外-No.006-2(2000年12月18日号)
まだまだあるある、たまごとコレステロールの誤認識。
以前に、この欄でも述べましたが、数々の文献で、人に対して、コレステ
ロールに関したまごは害ではなく、各種の生体機能に無くてはならないもの
であり、過食は論外ですが、たまごはむしろ食べるべき、というのが現在では
定説になりつつあります。
ところが、こともあろうに、大手製薬メーカー、田辺製薬が、病院、薬局
に対し、「控えたい食品の横綱は鶏卵」という大書きした食改善番付表を配
布するという失態を犯してしまいました。
これに対し関係団体が抗議(2000年12月15日)したところ、会社側は速
やかにミスを認め、謝罪し(同12月15日午後)、出回っている番付表は全て
回収し、他も焼却処分することを約束したそうです。
会社側が速やかにミスを認めたのがせめてもの救いですが、一流大手(?)
メーカーですら、こうしたミスを犯すのが現状です。 一般の多くの中小医
療機関ではまだまだ、この、たまごとコレステロールに関しての誤った定説が
根強く流布されているようです。
みなさま!!! 病院や薬局に番付表が回収されずに張り出されていたら
注意しましょう。 そこは、認識不足です。
(出来ましたら、その病院等をメールでお知らせいただければ嬉しいです。) |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.006(2000年12月1日号)
何のための 賞味期限 !!
月並みながら、師走。
毎年この時期は、養鶏やさんは相場の上がることを期待しています。
スーパ等が相次いで年中無休となる中、今さら、年末だから、お正月だから
でもあるまいと思いますが、事実、暮れになると相場は上昇するのでした。
しかし、そのスジの予想によると、今年は上がらないそうです。 なぜなら、
一部の大手の養鶏業者が大型貯卵庫を保有するようになり、相場の安いとき
(売れないとき)、保管しておいて、年末の高相場時に市場に出すと思われ
るからだそうです。 そうした、冷蔵庫から出てきたたまごの賞味期限にど
んな意味があるのでしょうか。 私ども、小規模養鶏には想像も出来ない
ことですが、もし本当としたら、ゆゆしき問題。 莫大なお金を投じ新聞広
告を打って賞味期限等の告知をおこなった業界、いえいえそれよりも何より
も、新鮮なたまごを求める消費者のみなさまへの重大な背信行為でしょう。
いかに冷蔵技術が進歩した現在でも、いったん、冷蔵保管されたものはや
はり”それなり”でしかありません。 ”生みたて”が最重要要件とさ
れるたまごにあって、売れる量(需要)以上を生産し、余るとこのようなこ
とを平気でやる。 たぶん、この世はチカラ、チカラのある自分だけ儲け
れば良い、というのでしょう。 しかし、こうしたことが、たまご全体の
信頼をどれほど失うことになるのか、わからないハズがないのですが。
レギュラー卵が売れなくなってきているとの由。これは単なる不景気によ
る消費減退、とだけで片づけるべきではないでしょう。 上述のような状態
に対しての、消費者のみなさまのたまご不信、と、ごく一部の業者のことと
はいえ、養鶏業界全体で受け止めるべきと考えます。
もちろん、消費者のみなさまにとっては安価なほうがよいことは当然です。
しかし、このような状態を消費者のみなさまが望んでいるとは思えず、その
スジの予想は、そのスジ共々、当たらない…事実でない…ことを願うばかり
です。
消費者のみなさま!!、たまご購入の際は、記載された”賞味期限”だけ
に頼らずご自分の眼でしっかりと品質を見極めてください。 よい品物を売
るお店を自らの眼で選んでください。、、それしか手だてはないようです。
まもなく21世紀。 めったにない…確実に100年に一度!!…節目の年。
新しい年は、たまご業界ともども、消費者に信頼される たまご であることを
信じます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.005(2000年11月1日号)
秋 ついこの前までの猛暑がウソのような、食欲の秋!!
我が家のにわとりもすっかり食欲モード。 業界フツーのやり方は、少しでも多くの
たまごを産ませるために、なるべく多くのエサを食べさせようとしますが、我が家で
は常にハラ八分。 なぜなら、経験的に、そのほうが鶏が疲れずに健康的だから。
(したがって、たまごも元気が良い。) 満腹に食べさせるより、産卵量はやや少な
いのですが、諸般の条件を総合的に勘案すると、やはりこのほうが良いようです。
ハラ八分……人も鶏も、いのちの原点はみな同じなようです。
こういう場合コンピューターでは、
卵餌比=(産卵量×卵価)/(餌食下量×エサ単価)
という計算をするのですが、その限りでは、餌を多量に(満腹)に
食べさせても、産卵量が多い方が、卵餌比が大きくなる(儲かる)
のですが、やはり、コンピューターには、いのちの原点は見えない
ようです。
もっとも、こんなことを云っていたら、現在の主流をなす、経済効率
最優先の超大型ウィンドレス養鶏法(*)などは、やっていけなくなっ
てしまうのでしょうか。 (*)当サイト内参照
”たまご”……他に何もなくても、そこから、一個の”いのち”が生まれる、そ
こが、たまごは完全食品といわれる所以でしょう。 こうした”いのち”のみなも
とを、経済動物ということでコンピューターだけで処理するのはいかがなものかと
考えますが。
閑話休題
先日、テレビ人気番組『発掘あるある大事典』の本、『あるある健康レシピ』(扶
桑社刊)を見つけました。 (2000年9月30日刊)
そこから、たまごに関する所を拾ってみました。
● 疲労回復……ビタミンB群 ● 疲れ目 ……ビタミンB群
● 脳力アップ…必須アミノ酸 ● 肝臓元気 …良質タンパク
● 冷え性改善…ビタミンB群 ● 不眠症 ……トリプトファン
● 肩こり ……良質タンパク ● 二日酔い …本にはないが、私の
体験で。
他にもいろいろ、、‥‥食事と健康が見えてきます。
また、この『発掘あるある大事典』のホームページ(当サイトリンクページより
ジャンプ可)があります。 そこのトップページから”たまご”で検索すると、
たまごへのさまざまな誤解、疑問が氷解すると共に、知られざる顔が見えてきます。
▲▼▲▼ ぜひオススメ!!! ナイショのたまごかけご飯コーナー ▲▼▲▼ |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.004_02(2000年10月)
号外!!
秋たけなわ。いよいよ、天高くおいしいたまごがますますおいしくなる季節。
(…いささか我田引水?…) しかしながら、コレステロール、アレルギーで、
たまごを食べることをためらっている人も多いことと思います。 そんな人に
朗報ひとつ。
朝日新聞9月25日(読まれた方も多いかと思われますが、)に
《卵》 栄養満点 制限はほどほどに
と、題してたまごを食べないことへの警告(?)署名記事が載っていましたのでその要点をご紹介いたします。
● 日米の栄養学者おのおのが、たまごを多食(1日3個以上)する人とそう
でない人と試験比較したところ、心臓病の発生率、コレステロールの影響
に差はなかった。
● 実際、“5,6個の目玉焼きをつまみに酒を飲む”というほどのたまご好きの
高木伸一氏(*)でも会社の検診ではいつも正常値。
(*)NTTデータ社員。卵好きが高じて、インターネットに
『たまご博物館』を開く。 (検索キーワード:たまご博物館)
● 従来のたまごによるコレステロール増加説は草食動物ウサギを使った実験
(1910年ロシア)で、人間には当てはまらない。
● 厚生省の国民栄養所要量改訂版で、「通常の人は制限する必要はない」と
された。
● アトピーに関しても、原因がたまごではないことも多く、また、成長して
アトピーが治ったのに気付かず、不必要な食事制限を続けているケースが
ある。
● そのことに気づかず、たまご、牛乳を含まない食事を続けた結果ビタミン
不足疾患となった。
● たまごや牛乳でアレルギーが出ることがあるのも確かだが、あまり神経質
になりすぎると栄養障害をおこしやすい。
● たまごを食べると、卵黄中のコリンとビタミンB12で、記憶物質アセチル
コリンが増え、アルツハイマー病の改善に顕著な改善が見られた。
以上のような内容でした。
いずれにしても、特別な高脂血症体質、はっきりとしたたまごアレルギーの人以外は完全栄養食といわれる、栄養満点のたまごの過剰敬遠はやめたほうがよいようです。最近では“この卵はアレルギーでも食べられます”といういわゆる特殊卵がいろいろ出回っているようです。
もちろん、ワガ“たかはしたまご”もそのひとつ。←詳しくは当サイトをご覧ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.004(2000年10月1日号)
秋の長雨も終わり、チョメチョメ心とアキの空、いえいえ、天高く馬肥ゆる秋。
わが家の鶏も、夏の暑さを乗り越えて、元気いっぱいに秋モード。
この夏の暑さにはどなた様も、卵の鮮度管理には気を遣われたことでしょう。
ところで、市販のたまごはパック詰めの際に、たまご問屋さん(GPセンター)で
洗卵してありますが、本来は洗わない方がよいこと、ご存じでしょうか。
洗わない方が衛生的というのもヘンなハナシなのですが、、、卵の殻には気孔
と呼ばれる孔が無数にあり、更にその外側をクチクラ層という薄い膜でおおわれ
ています。 この膜は、殻を通してバイキン等の侵入を防ぐ働きをもっています。
ところが、洗卵するとこのクチクラ層まで洗い落とされてしまうのです。また、
この膜は呼吸の調節作用も担っており、クチクラ層がはがれて気孔がむき出しに
なると水分、炭酸ガスが過度に蒸散し卵内部のバランスがくずれ(鮮度が落ち)
卵が死んでしまいます。しかも、気孔を通し卵の内部までバイキンが侵入し卵が
腐りやすくなってしまうのです。
また、別の視点から見ると、メンドリがひなを孵化させるため温める3週間の間
バイキン等が入らないで安全に経過出来るように、ということで自然の摂理とし
て、クチクラ層があるのです。
前回この欄で述べたHACCP 等は、こうした自然の摂理に強引に反するもので
あり、大げさにいえば、人間のおごりとすら、私には思えてなりません。 HAC
CPを無視し、不衛生でよいというのではありませぬ。 たまごを取り扱う全ての
ステージで、たまごとして当たり前の配慮をすればよいことであり、宇宙仕様の
衛生基準HACCPをわれわれの日常生活に当てはめるべきではないと信じます。
(HACCP 準拠の工場でも事故はおきました。)
もっとも、多人数のいる大型農場で、効率優先経営では、やはりこうした、シス
テマチックな方法でないと成り立たないのかもしれませんが。
‥‥‥前回のこの欄参照‥‥‥
この、クチクラ層をこのH.P の中で見ることが出来ます。ぜひごらんください。
クチクラを洗いおとすことの危険性を実感していただけることでしょう。
【「たかはしたまごはこんなとこ」→「たかはしたまごのいちにち」】参照 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.003(2000年9月1日号)
いよいよ9月。今年の暑さはさすがに我が家の鶏も、元気とはいえ、食傷気味の様子。 報道によれば、大量の鶏が熱死したところがあるとか、、、。人間の経済効率のギセイになったようで、実に悲しい限りです。 こころよりおオクヤミ申し上げる次第です。
今年の夏は、例の、雪印、トーチクハム等の影響で当該商品だけでなく、いわゆる、”なまもの”に対しての信頼が大きく崩れてしまったように思います。 いずれの事故も、作業担当者、責任者がプロとしての自覚を持っていれば起こり得なかったように思えてなりません。ヒューマンエラーとしか言いようがないでしょう。
マニュアル、HACCP等も私どものような家業とちがい、大きな会社ではある程度は必要ではありましょうが、あまりにもそれらの頼りすぎた結果でしょう。
HACCPはアメリカNASAが宇宙計画の中で作られた基準とか。 私見ではありますが、我々が日常生活する上で、そこまでのことが必要なのでしょうか。 人間はもともと、良くも悪くも、微生物の中で生命を維持しています。 不衛生で良いというのでは断じてありませぬが、あまりにことがすすむと、人間がますます弱体化していくように思えてなりません。(ある識者が新聞でも述べておられましが、)
マニュアル、HACCP等の強化よりも、ヒューマンエラーをなくす努力こそが、いま最も求められているような気がしてなりません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.002(2000年8月1日号)
夏こそ“たまご”
文字どうりの猛暑の連日。 私の体験からの、とっておきの夏バテ解消法を紹介いたします。
ズバリ!!、“たまご”です。 我田引水のようで恐縮ですが、私自身夏の暑さは苦手で、食欲が無くなり、どうしても、バテてしまいがちです。そんなとき“たまご”です。それもなるべく“生たまご”。 たまご焼き等、加熱されたものよりもはるかに夏バテ撃退効果が大きいようです。 私の朝食は”生たまご”二つ、です。論より証拠。ぜひ一度お試しくださいませ。
夏季の たかはしたまご の取り扱いについて。
通常ですと、”たまごは冷蔵庫には入れないでください。”とお話しておりますが、この時季はやはり冷蔵庫に入れたほうが良いでしょう。 入れなくても、すぐに食べられなくなるようなことはありませんが、早く水っぽくなってしまいます。 特に”生たまご”の時は”見た目”もおいしさのひとつですので、白身、黄身がこんもりと盛り上がっている方がよいでしょう。
尚、冷蔵庫に入れるときは、扉部分にある、”たまご置き場”には置かないでください。ここは、扉の開け閉めの際に、大変、温度変化、振動(特に閉めるとき)が大きく、たまごにとっては大変キビシイ場所です。 冷蔵庫内では、適当な湿度があり、野菜室がベストでしょう。
たかはしたまご に成り代わりましてお願い申し上げます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
たかはしたまご便り-No.001(2000年7月7日号)
はじめまして、 たかはしたまご です。
深まった緑の中に、真っ赤な太陽の予感をおぼえる候となりました。
この時期、本ホームページを開設出来た幸運をすなおに喜ぶと共に、ご尽力いただいた経営コンサルタントの小林一博先生、柴田書店イータリンク(株)他の皆様に感謝感謝の今日この頃です。
さて、‘たまごは物価の優等生’の言い回しの一方で、昨今、いわゆる高級な
(!?)‘特殊卵’が多数出回っております。 曰く、ビタミン入り、DHA入り、木酢入り、カテキン入り、HACCP、高原の澄んだ空気、水、放し飼い、薬品不使用、NON-GMO, ete、etc、、、、。
それぞれが‘良いたまご’だとは思いますが、いくつかを試食してみると、どうにも物足りなさを感じて仕方ありません。
“昔のたまごは安心でおいしかった”‥‥よく言われる言葉ですが、そうした言葉に応えるべく、何かを一つだけ特別に強化する、というのではなく、
★ 安心、安全のため、鶏の健康のため、そしておいしいたまごのため、
“自然の恵み”をふんだんに取り入れて、
★ 「地たまご」、「こんもりとした黄身」等の、テレビのグルメ番組でよく使
われる単なる‘言葉’や‘見せかけ’の 品質だけではなく、“本当の安
心、本当のおいしさ”を求めて、
★ 鶏種に、飼料、水に、環境に、試行錯誤の10余年間でした。
ようやく、どうにか皆様に評価していただけるようなたまごになったような気がします。
あれこれと、案じることなく
●●“とにかく不安のない、とにかくおいしいたまご”●●
をご希望の方、ぜひ一度だけでもお試しいただければと存じます。 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|